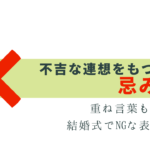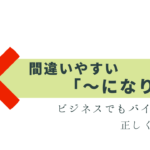- 更新日:2023/07/04
「二十四節気」は、春夏秋冬をさらに分けた、季節の変化を表したものです。
24個それぞれ簡単に見ていきましょう。
ひとことで表すと
「二十四節気」
| 季節 | 名称 | 日付 | 季節 | 名称 | 日付 |
| 春 | 立春 | 2月4日頃 | 秋 | 立秋 | 8月8日頃 |
| 雨水 | 2月19日頃 | 処暑 | 8月24日頃 | ||
| 啓蟄 | 3月6日頃 | 白露 | 9月8日頃 | ||
| 春分 | 3月21日頃 | 秋分 | 9月23日頃 | ||
| 清明 | 4月5日頃 | 寒露 | 10月9日頃 | ||
| 穀雨 | 4月20日頃 | 霜降 | 10月23日頃 | ||
| 夏 | 立夏 | 5月6日頃 | 冬 | 立冬 | 11月8日頃 |
| 小満 | 5月21日頃 | 小雪 | 11月23日頃 | ||
| 芒種 | 6月6日頃 | 大雪 | 12月7日頃 | ||
| 夏至 | 6月22日頃 | 冬至 | 12月22日頃 | ||
| 小暑 | 7月8日頃 | 小寒 | 1月6日頃 | ||
| 大暑 | 7月24日頃 | 大寒 | 1月20日頃 |
詳しい解説
二十四節気
読み方:にじゅうしせっき
1年を太陽の動きに合わせて、24に分け、
それぞれに季節の名称を与えたものです。
旧暦と季節を合わせるために名付けられました。
そのため現在、
私たちが体感する気候や季節感とは合わない時期もあります。
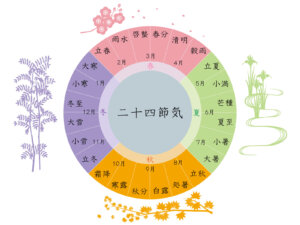
春
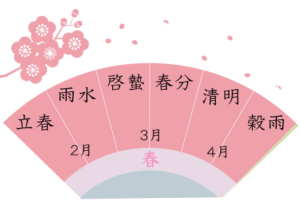
立春
読み方:りっしゅん
日付:2月4日頃
暦の上では、この日から春が始まります。
節分の翌日にあたり、
八十八夜や二百十日などの基準になります。
雨水
読み方:うすい
日付:2月19日頃
雪が解けて水となり、草木の芽が出始める頃という意味です。
啓蟄
読み方:けいちつ
日付:3月5日頃
この日、冬ごもりをしていた地中の虫が、
気候が暖かくなって穴から出るという意味です。
春分
読み方:しゅんぶん
日付:3月20日頃
太陽が真東から出て、真西に沈み、
昼と夜の時間が、ほぼ等しくなります。
春のお彼岸の真ん中です。
清明
読み方:せいめい
日付:4月4日頃
天地には清らかで明るい空気が満ちて、
萌え出た草木の芽がはっきりしてくる時季です。
穀雨
読み方:こくう
日付:4月20日頃
春の雨がさまざまな穀物をうるおすという意味です。

夏

立夏
読み方:りっか
日付:5月6日頃
暦上では、この日から夏です。
小満
読み方:しょうまん
日付:5月21日頃
草木が茂って、天地に満ちるという意味です。
芒種
読み方:ぼうしゅ
日付:6月6日頃
イネや麦など、芒(のぎ)がある穀物をまくという意味です。
梅雨に入る頃にあたり、昔、田植えはこの頃に行われました。
夏至
読み方:げし
日付:6月22日頃
北半球では、一年中で最も昼が長く、夜が短くなります。
小暑
読み方:しょうしょ
日付:7月8日頃
この日から暑さが募ってきます。
大暑
読み方:たいしょ
日付:7月24日頃
一年中で最も暑さが厳しい時季です。
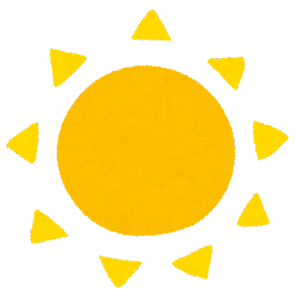
秋
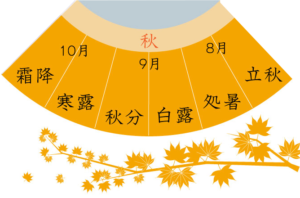
立秋
読み方:りっしゅう
日付:8月8日頃
暦の上では、この日から秋です。
この日以降の暑さを、残暑 といいます。
処暑
読み方:しょしょ
日付:8月24日頃
ようやく暑さがおさまる時季という意味です。
白露
読み方:はくろ
日付:9月8日頃
草木の露も白く見え、秋らしい気配が加わります。
夏から秋へと移り変わる時季です。
秋分
読み方:しゅうぶん
日付:9月23日頃
太陽が真東から出て、真西に沈み、
昼と夜の時間がほぼ等しくなります。
秋のお彼岸の真ん中です。
寒露
読み方:かんろ
日付:10月9日頃
草木の露が、ことさら冷たく感じられるようになります。
北国では、初氷が張る頃です。
霜降
読み方:そうこう
日付:10月23日頃
朝と夕方の気温が下がり、霜が降り始める時季です。

冬

立冬
読み方:りっとう
日付:11月8日頃
暦の上では、この日から冬です。
小雪
読み方:しょうせつ
日付:11月23日頃
寒い風が吹き始め、山地には雪がちらつくようになります。
大雪
読み方:たいせつ
日付:12月7日頃
北風が強く吹き、平地にも雪の降る時期です。
冬至
読み方:とうじ
日付:12月22日頃
北半球では、一年中で最も昼が短く、夜が長くなります。
小寒
読み方:しょうかん
日付:1月6日頃
この日から、寒さが募ってきます。
また小寒から節分までの30日間を、「寒の内」といいます。
大寒
読み方:だいかん
日付:1月20日頃
一年で最も寒さが厳しい時季です。