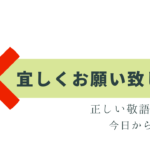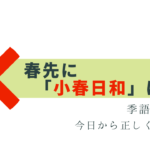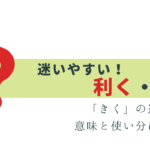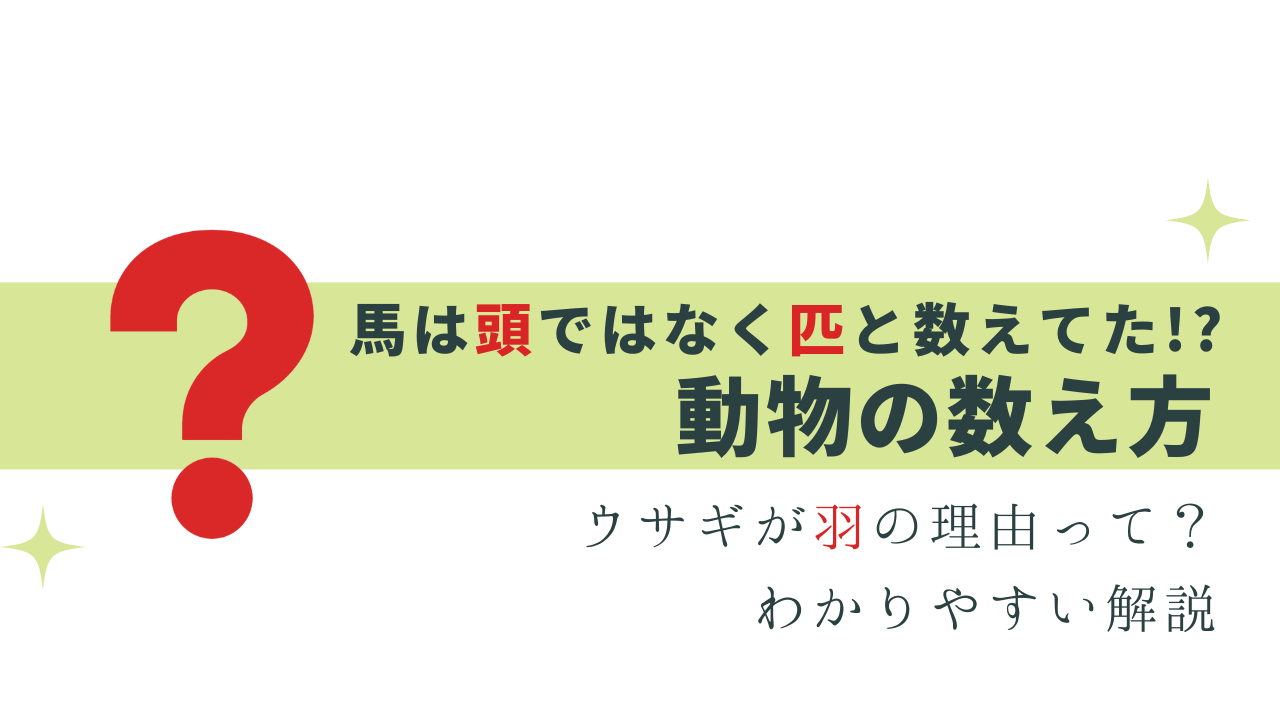
頭・羽など、動物の数え方は死んだ後に残る部位で決まる説について、
一時期SNSで話題になりました。
考えてみれば、
・牛 → 頭は食べない
・鳥(鶏) → 羽は食べない
よって、この説に納得しそうですが、
実際どうなのか調べてみました。
今回は、動物の数え方について、学んでいきましょう。
ひとことで表すと
・大型の動物 → 頭
・中型・小型の動物 → 匹
<歴史>
・昔は、馬を「匹」と数えていた
・明治時代に、英語圏ではhead で数えているのを見て、頭 と訳した
・大型の動物が、匹 → 頭 に変化した
詳しい解説
頭 の前に、動物を数える匹 の由来から、見ていきます。
馬は匹で数えていた
匹
読み方:ヒツ・ヒキ
意味:
(1) 牛・馬などを数える単位
(2) 対になっている二つのもの
馬の尾の象形、つまり馬のお尻と尻尾の形から生まれた漢字です。
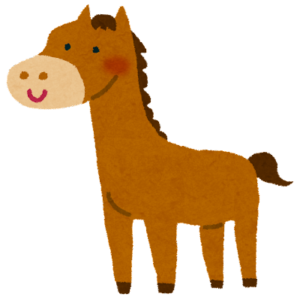
むかしむかし人間は、荷車や農耕など、馬と一緒に行っていました。
- (馬のように) 2つに割れたお尻の対を持つもの
- 綱につないで引く動物
これらの理由から、馬を「匹」と数えました。
それから、馬だけではなく、動物全般を数えるときは、
「匹」を使うようになり、今日に至ります。
頭 になった理由
現代私たちは、大型の動物を、「頭」と数えます。
実は、1頭・2頭…と数えるようになったのは、
英語の影響を受け始めた明治時代からです。
ヨーロッパやアメリカでは、
放牧に出した牛の数が合っているか確かめるとき、頭の数を確認します。
20 head of cattle
20頭の牛
ちなみに、複数扱いなのでheads ではなく、head が正解。

直訳して「頭」と呼び、
大型の動物の一般的な数え方として「頭」が定着しました。
もともと「匹」で数えていた馬も、
次第に「頭」に変わったという歴史があります。
ウサギを羽で数える理由
鳥類ではないウサギを数えるとき、
1羽・2羽…と、なぜ「羽」を使うのでしょうか。

理由は諸説あります。
獣肉食が禁止されていた時代に、
(1) 二本足で立つウサギを、鳥類と見立てて食べたから。(2)ウサギの大きくて長い耳が、鳥の羽に見えるから。
(3)ウサギ = 兎(ウ) + 鷺(サギ)と解釈して、鳥とこじつけて食べたから。
慣用的に「羽」を使いますが、
動物として数えるときは、「匹」でも問題ありません。
まとめ
今回は、動物の数え方について見てきました。
今でこそ大型の動物を数えるときは、頭 ですが、
明治時代より前は、匹 だったんですね。

参考文献
・広辞苑第6版
・明鏡国語辞典
・数え方の辞典
・新漢語林
・ジーニアス英和辞典 第4版
・ロングマン英和辞典
・プログレッシブ和英中辞典 第3版