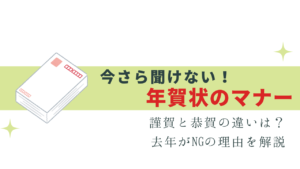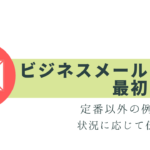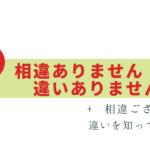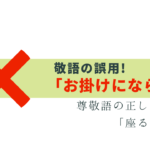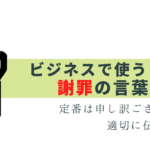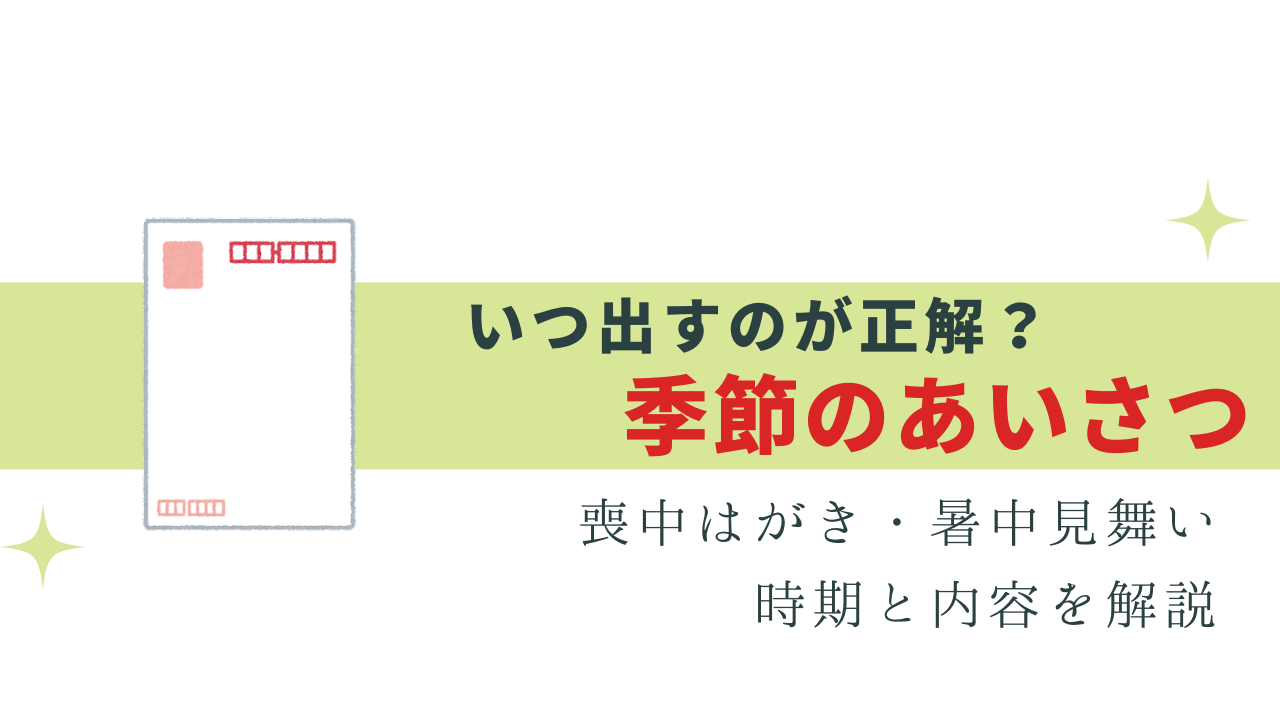
電話やメールなどの連絡が多くなり、
年賀状を出すことは、少なくなったかもしれません。
とはいえ、季節の挨拶として、
手紙やハガキを出す機会もあると思います。
いざという時のためにも、
今回は、 季節の挨拶について見ていきましょう。
ひとことで表すと
| 季節の挨拶 | 時期 | 内容 |
| 年賀状 | 1/1〜1/7 | 新年の祝い |
| 寒中見舞い | 1/8〜2/3 | ・年賀状の出し忘れ、喪中欠礼を出さなかったお詫び ・寒さに伴い、相手を気遣う |
| 余寒見舞い | 2/5〜2月下旬 | 寒中見舞いに間に合わなかった場合(内容は同じ) |
| 暑中見舞い | 7/7〜8/6 | 暑さに伴い、相手を気遣う |
| 残暑見舞い | 8/7〜8月下旬 | まだまだ続く暑さを受けて、相手を気遣う |
| 喪中欠礼 | 11月下旬〜12月下旬 | 喪中のため、新年の挨拶を遠慮する |
詳しい解説
年賀状
年賀状は、
新しい年の訪れを祝い、健康と幸せを願う言葉を述べるもの。
贈るタイミングは、元日〜松の内(1月7日)までです。
書き方のマナーなど、詳しいことは以下に書いています。
合わせて読んでみてください。
寒中見舞い
読み方:かんちゅうみまい
贈るタイミングは、松の内が明けた1月8日〜2月3日の節分まで。
(自分が)喪中と知らず、年賀状を送ってくれた人に対して、
喪中欠礼を出さなかったお詫びを書き添えます。
逆もしかりで、年賀状の出し忘れや、
相手が喪中と知らず、年賀状を贈ってしまった場合も同様です。
また現在では、
特に寒い地方に住む相手の健康を気遣う内容を多くなりました。
余寒見舞い
読み方:よかんみまい
“余寒”とは、立春後まで残る寒さのことです。
贈るタイミングは、立春を過ぎた2月5日〜2月下旬まで。
年賀状や、寒中見舞いの時期を過ぎてしまった場合に贈ります。
寒中見舞いと同様に、お詫びの言葉を添えましょう。
補足として、東北地方や山陰地方など、
3月でも寒い地域であれば、3月6日の啓蟄までに届けばOKです。
・二十四節気のひとつで、太陽暦の3月6日頃
・冬ごもりをしていた虫が地上に出るという意味

暑中見舞い
読み方:しょちゅうみまい
一年で最も暑さが厳しいといわれている時期に、
親戚や知人などの相手を気遣う手紙です。
暦の上では、夏の土用にあたる、立秋(8月7日頃)の前18日。
しかし現在は、実際の気候に合わせて、
梅雨が明けた頃〜立秋の前日までに出すことが多いです。
贈るタイミングとしては、小暑の7月7日〜立秋前日の8月6日まで。
日付の書き方は、「令和◯年 盛夏」です。
お中元を贈る場合は、
お中元の挨拶を兼ねて、暑中見舞いとしても問題ありません。

残暑見舞い
読み方:ざんしょみまい
”残暑”とは、立秋を過ぎても残っている暑さのことです。
なかなか終わらない、まだまだ暑い日が続くことを受けて、
相手を気遣う手紙です。
贈るタイミングは、立秋の8月7日〜8月下旬まで。
日付の書き方は、「令和◯年 晩夏」です。
喪中欠礼 (喪中はがき)
読み方:もちゅうけつれい
“喪中”は、一般的に家族の死後丸1年間をさし、
年賀状を含めた祝い事を控えます。

その年に家族の不幸があった場合、年賀はがきを出します。
年賀状のやり取りをしている人へ、
新年の挨拶を遠慮する旨を伝えましょう。
贈るタイミングは、年賀状の準備をはじめる11月上旬〜12月上旬まで。
「喪中につき、新年のご挨拶は遠慮申し上げます」
というような表現にします。
まとめ
今回は、季節の挨拶について見てきました。
いざ書くタイミングで困らないように、
時期や内容を抑えておきたいですね。

参考文献
・広辞苑第6版
・明鏡国語辞典
・類語例解辞典